

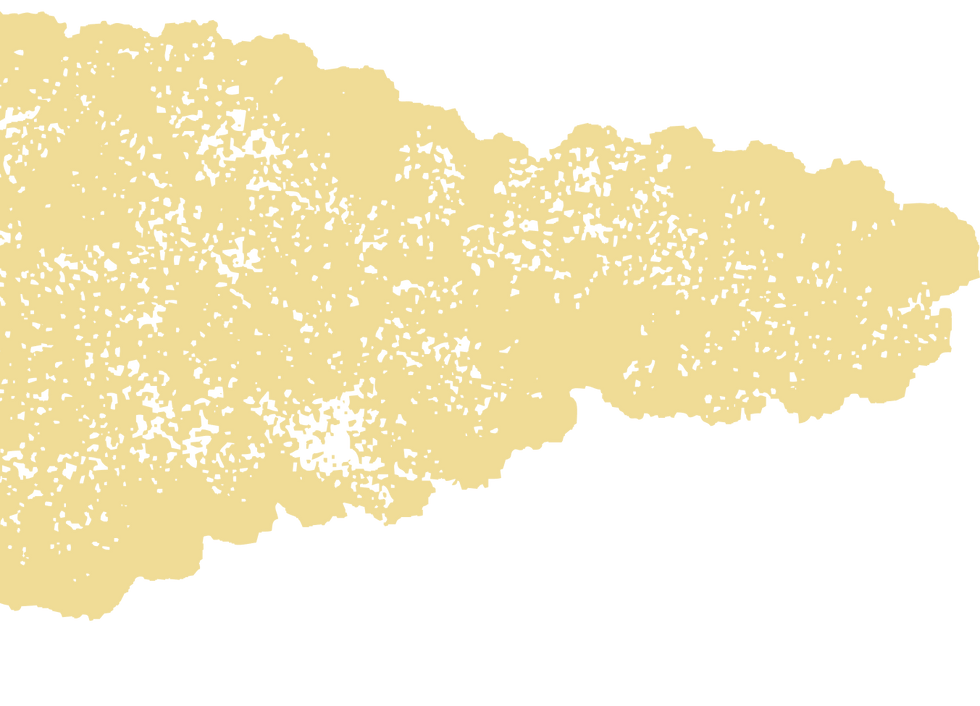
-
応神天皇:勝負の神。文武の神。厄難除け、子孫繁栄、交通安全等
-
仲哀天皇:勝負の神。家運隆昌、夫婦円満、家内安全
-
神功皇后:勝負の神。安産、子育て、芸能上達、夫婦円満、美の神


-
大国主命:縁結びの神。子授け、病気平癒、商売繫盛
-
伊弉諾命:縁結び、国生みの神、夫婦円満、厄難避、子宝
-
伊弉冉命:縁結び、国生みの神、夫婦円満、厄難避、子宝
-
稻倉魂命:五穀豊穣の神。商売繫盛、諸願成就、家内安全
-
保食命:食物の神。養蚕の神
-
大山祇命:長寿の神。良縁、酒造守護、水源の神



創建より当社に伝わっていたとされる舞楽。八人の早乙女にて奉仕されるおしとやかな舞だったとされている。現在、舞は伝承されていないため早急な復興が待たれている。



当社の獅子舞は「七五三の舞」ともいわれ七つ前に進み五歩下がるそして再び三歩前に進む舞である。古来は旧荒砥町の重要な物産でもあった「繭」「青麻」の相場を獅子舞の疾走する様(半夏段々平)をもって占い決めていたと言われている。いつから当社にて行われているのかは不明である。現在使用している獅子頭は明治35年当地崇敬者よりご奉納いただいたものである。
寛治元年(1087年)
源義家公が東夷征討の際当地にて敵軍の勢いが強く進軍出来ずにいると源義家公の夢に八幡大神が現れ、素晴らしい作戦を授けられた。これに従い見事敵軍を打ち破り進軍が可能になる。その後御楯付近にて弓矢を立て八人の乙女に舞楽を奏させ京都・石清水八幡宮を遥拝させたことが当社の起こりであり社名の由来と伝えられる。
文明2年(1470年)
伊達晴宗家臣、桑島上野守、社殿を修営。
天文10年(1541年)
石那田村・馬場村・菖蒲村・下山村・佐野原村・大瀬村・十王村・滝野村・萩野村・中山村・畔藤村・広野村にて構成される郷の「新戸郷総鎮守」となる。
明和7年(1770年)
現存する参道石階段と石畳を舗装。
明治5年(1872年)
石那田村・村社に列格。時同じく国家の政策により全国的に八幡系統の社名を統一され当社も類にもれず社名を「八幡神社」へ改称する。
明治12年(1879年)
郷社に昇格。
明治34年(1901年)
旧暦9月15日、辰の刻(午後7時) 拝殿へ落雷。それに伴い本殿・拝殿他全焼。歴史書・宝物・獅子頭他全て焼失する。
明治35年(1902年)
本殿 仮殿を造営。拝殿再建する。同じく獅子頭四頭を当地崇敬者より寄進される。一頭は所在不��明となっている。
明治43年(1909年)
本殿再建。遷宮祭が行われる。
大正6年(1917年)
神饌幣帛供進神社に指定。国家より神社合祀令が発令される。これにより石那田村鎮座・村社「御楯稲荷神社」、村社「深山神社」無格社・「瀧本稲荷神社」下山村鎮座・村社「庭渡神社」村社「熊野神社」佐野原村鎮座・「稲荷神社」が当社に合祀される。
平成3年(1991年)
拝殿屋根葺き替え竣功
令和7年(2025年)
153年の時を経て社名を「八乙女八幡神社」へ改称
